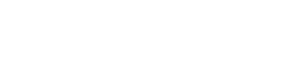日本の近代文学は名古屋から始まった【その2】
<二葉亭四迷>
二葉亭四迷(本名長谷川辰之助)は、江戸市ケ谷合羽坂尾張藩上屋敷で、父・長谷川吉数、母・志津の子として元治元年(1864)に生まれた。
明治元年(1868 4歳)、明治維新による諸藩引き払いのため、父だけが東京に残り、母と共に父母の故郷の名古屋に移住。名古屋ではまず母の弟にあたる後藤有常の私塾で漢学を学んだが、この漢学(儒教)の感化が四迷の生き方に大きな影響を及ぼしていくことになる。
明治4年(1871 7歳)、名古屋県洋学校(名古屋藩学校が改称)に入学し、林正十郎及びフランス人ムーリエについてフランス語を学ぶ。
明治5年(1872 8歳)、愛知県洋学校(名古屋県洋学校が改称)を中退し、上京。麹町区飯田町消防屋敷跡に11歳まで住む。
その後、島根県吏に任じられた父に伴い、松江で3年暮らし、明治11年に帰京。いくつかの私塾で漢学と数学を学びながら、陸軍士官学校を受験。四迷は軍人となって、「将来日本の深慮大患」に直接応える人間になろうとしたのであるが三度不合格となる。理由は強度の近視だったためと伝えられている。軍人になることを諦めた四迷は、語学をもって深慮大患に当たる外交官になろうと、
明治14年(1881 17歳)、東京外国語学校ロシア語部に入学する。
四迷はここでロシア文学に出会う。教師ニコライ・グレーは一冊しかないツルゲーネフ、ゴーゴリ、トルストイなどの文学作品を毎日、教壇から朗読し、学生たちに聞かせて、作中人物の性格批評を文章にまとめさせるという授業を行ったといわれる。逍遥と同様、四迷も耳から近代文学を学んだのである。
明治19年(1886 22歳)、四迷は同郷の先輩坪内逍遥を訪ねる。『小説神髄』の文学理論に対して、自分の疑問とするところを直接問い質そうとやって来た無名の四迷を逍遥は謙虚な姿勢で受け入れ、のみならず四迷の文学理論に感心し、それを原稿にまとめさせ「中央学術雑誌」に『小説総論』として発表させた。
以後、四迷は頻繁に逍遥宅を訪れ、文学論を戦わせ、また三遊亭円朝の落語を参考にしながら
明治20年(1887)、日本で初めての言文一致体による小説『浮雲』を著した。良心的近代知識人の苦悩をテーマとしたことや細かな心理描写はこれまでの日本文学には無いものであった。
翌21年には、ツルゲーネフからの部分訳『あひゞき』『めぐりあい』を発表するが「原文にコンマが三つ、ピリオドが一つあれば、訳文にも亦ピリオドが一つコンマが三つという風にして原文の調子を移そうとした」(「余が飜譯の標準」)もので、森鴎外をして「あゝでなくては」と言わしめた厳しい態度が、日本における翻訳文学の端緒を開いたのであった。
しかし「維新の志士肌的気質」を持ち、憂国に燃える四迷は、文学には直接の実感が無いとして、以降は翻訳のみを手がけるだけとなり、
小説は明治39年に晩年の名作『其面影』、40年に『平凡』を書いた限りとなる。文学を離れた四迷は「直接の実感を得るため」、内閣官報局雇員として英字新聞の翻訳や、陸・海軍大学校でのロシア語教授、大阪朝日新聞特派員などをしたりしたが、
明治42年(1909 46歳)、ロシアからの帰国の洋上で病没した。